子どもの定期予防接種
予防接種法で定められている定期予防接種は、個別に実施指定医療機関で、無料で受けられます。
予防接種を受ける時は、予防接種予診票つづり(予防接種手帳)の注意や冊子「予防接種と子どもの健康」または予防接種の説明書などをよく読んでから受けましょう。
予防接種できる医療機関

- 国分寺市内の実施指定医療機関
下記の定期接種実施指定医療機関(PDF)でご確認ください。
- 【BCG以外の予防接種】立川、国立、小平、小金井、東村山、昭島、東大和、武蔵村山、清瀬、狛江市の実施指定医療機関
国分寺市以外の実施指定医療機関は、希望する医療機関の所在地がある市役所のホームページをご確認ください。
(注釈)里帰りや入院などの事情で、上記の実施指定医療機関以外での接種を必要とする場合、健康推進課へ接種前に申請していただき、接種後に接種費用の申請を行うことで還付を受けることができます(助成上限額あり)。詳しくは、「国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成制度」のページをご確認ください。
定期予防接種の対象ワクチン
接種できる年齢、予防効果のある病気、注意点などは、各ワクチンのページをご確認ください。
年齢「〇歳未満」は「〇歳の誕生日の前日まで」接種ができます。例えば、1歳未満となっている場合は1歳の誕生日前日まで接種ができます。原則として、接種できる年齢を過ぎると無料で接種できませんので、接種間隔を過ぎた場合は対象年齢内に速やかに接種してください。
- ロタウイルス
- Hib(ヒブ)
- 小児の肺炎球菌
- B型肝炎
- 五種混合(四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib(ヒブ)))・四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)・二種混合(ジフテリア・破傷風)
- BCG(結核)
- 水痘(水ぼうそう)
- 麻しん風しん混合(MR)
- 日本脳炎
- HPVワクチン・定期接種(子宮けいがん予防)
- HPVワクチン・キャッチアップ接種(子宮けいがん予防)
(注釈)生ワクチン(BCG・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・水痘・おたふくかぜ・帯状疱疹)を接種した後、生ワクチンを接種する場合は27日以上空けて接種する必要があります。生ワクチンの同時接種は、医師が認めた場合、可能です。そのほかのワクチンどうしの接種間隔はありません。
接種時の持ち物
- 予診票(事前に必要事項に記入、署名してください)
(注釈)生後2か月になるまでに、小学校就学前までに受ける予防接種の予診票をつづりにして郵送しています。それ以降の予防接種の予診票は、対象年齢になりましたらお送りします。詳しい送付時期は、ワクチンごとのページをご確認ください。お手元に予診票がない場合は予診票発行の申請が必要です。詳しくは下記の「予診票の発行」をご確認ください。 - 母子健康手帳
- 【13歳以上16歳未満のお子さんが保護者の同伴なしに接種する場合】保護者同意書
(注釈)保護者同意書は、13歳以上16歳未満で、子宮けいがん予防接種を保護者が同伴しないで受けたい場合に使用します。予診票の保護者自署欄および保護者同意書の両方に署名して、接種当日お子さんに持たせてさせてください。両方に署名がないと予防接種が受けられません。
【転入してきたかた・予診票が手元にないかたへ】予診票の発行
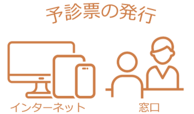
国分寺市・近隣市10市の実施指定医療機関での接種には、国分寺市の予診票が必要です。
国分寺市に引っ越し(転入)したかた、紛失などで国分寺市の予診票をお持ちでないかたは、接種前にインターネットまたは窓口で申請いただき、予診票を入手してください。
-
インターネットでの申請
-
電子申請システム LoGoフォームから申請してください。
申請の際、母子健康手帳の出生証明書(1ページ目)、予防接種ページ(全ページ)の写真を添付していただく必要があります。
申請に不備がない場合、原則1週間から10日程度でご自宅に郵送します。
-
窓口での申請
-
母子健康手帳をお持ちのうえ、月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後5時までに、健康推進課(泉町2-2-18国分寺市役所2階)で申請してください。
(注釈)インターネット・窓口での申請が難しい場合、国分寺市内の実施指定医療機関での接種であれば、医療機関で入手できる可能性があります。事前に医療機関に予診票の在庫を確認してください。また、医療機関へ行く際は、母子健康手帳と国分寺市内に住所があることが分かる本人確認書類または住民票などをお持ちください。
予防接種と副反応
ワクチンは生体にとっては異物であり、接種による副反応は避けられません。予防接種を受ける際は予防接種予診票つづり(予防接種手帳)と一緒に送付している「予防接種と子どもの健康」や予防接種説明書などをお読みいただき、お子さんの健康状態のよい時に保護者の判断のもとで接種を受けてください。
- 通常みられる副反応
ワクチンの種類によっても異なりますが、局所反応として注射部位の発赤・しこり・疼痛などがみられます。通常数日以内に自然に治るので心配する必要はありません。詳しくは、ワクチンごとのページをご確認ください。 - 重い副反応
予防接種を受けた後、接種局所のひどいはれ、高熱、ショック・アナフィラキシー様症状(通常、接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)、ひきつけ・けいれんなどの症状があったら医師の診察を受けてください。お子さんの症状が厚生労働省令に定める症状を診断した場合には医師から厚生労働省へ報告されます。
予防接種による健康被害救済制度
定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外は、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。
(注釈)子宮けいがん予防接種のキャッチアップ接種は、定期接種となります。
ワクチン接種後に体調の変化があった場合には、すぐに医師に相談してください。副反応により治療が必要になった場合には健康推進課までご連絡ください。
予防接種のスケジュール管理はアプリ「ぶんじ子育てナビ」をご利用ください
予防接種の事前のお知らせ、スケジュール管理、忘れ防止アラート機能で、予防接種のスケジュールをサポートします。無料での接種期間を逃さないためにもご活用ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-312-8628 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
